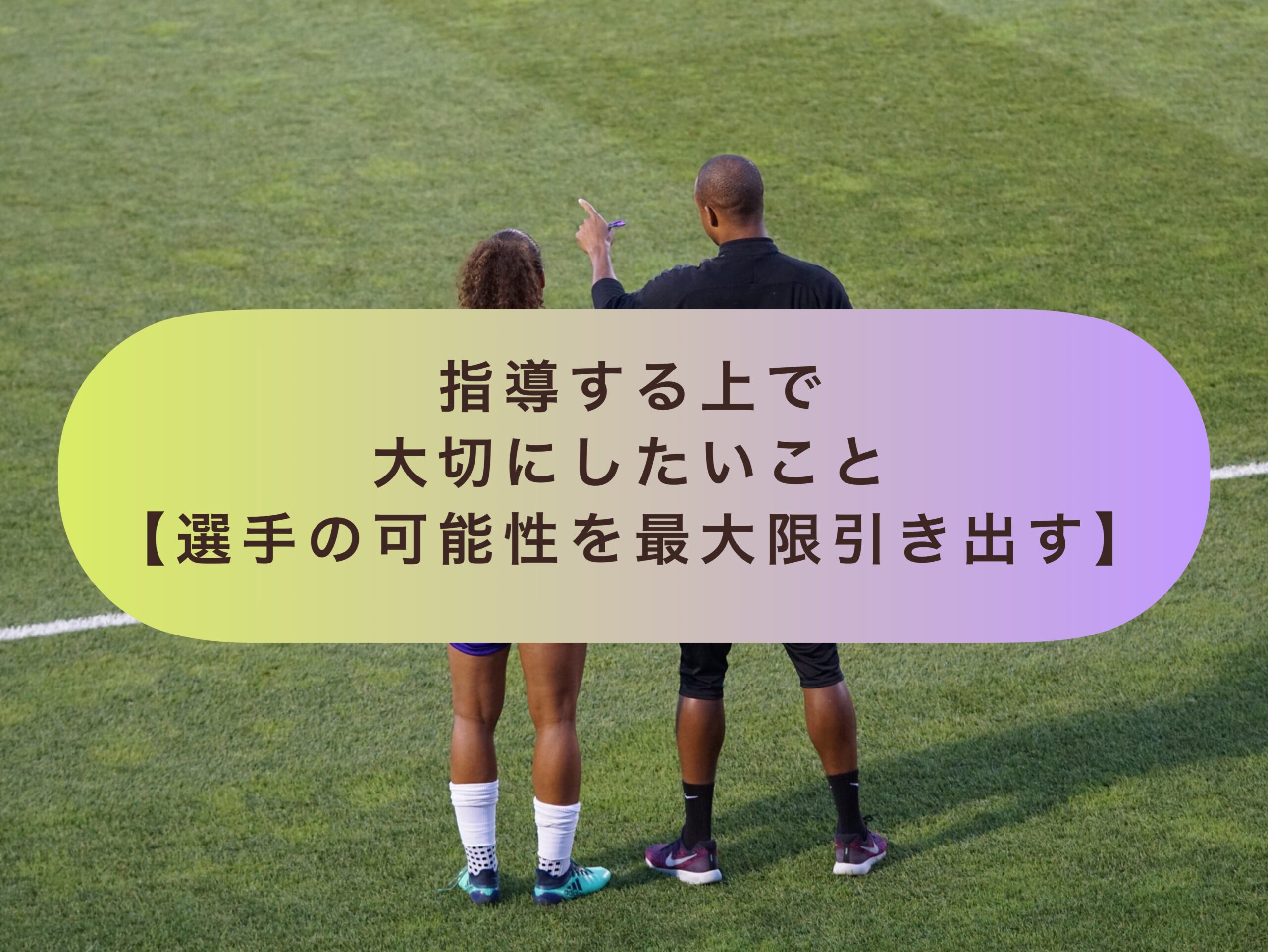こんにちは!豊橋の陸上専門整体サロン ライオンハートの れお です。
私は、陸上競技短距離を小学4年生(2008)に地元の陸上クラブに入会し、
2021年現在までさまざまトレーニング方法に取り組んだり、コーチに指導していただいたり、
書籍や研究を読んできました。
大きく指導の方法は、2種類あります。
・定着型指導:「記録」や「技」のレベルを評価すること。
→例:Aさんは4回の授業で跳び箱を5段飛べました。Bさんは3段飛べました。
・生成型指導:
1.これをやれば誰でも足が速くなる…!
結論から言いますと、これをやれば速くなる!という方法は存在しないと考えます。
為末 大さんの著書である「限界の正体/SB Creative株式会社出版」の中で、このようなことを述べております。
世界のトップスプリンターの共通点は
限界の正体 自分の見えない檻から抜け出す法 [ 為末 大 ]
「足が速いこと」以外に見つけることができなかった。
つまり、その選手にはその選手にしか存在しない感覚や強みがありますし、その選手には必要でないこともあります。
選手の発達・骨格・特性を確認して、選手の知らない動作を分析し、選手に応じた反応を引き出しすことが究極になります。
そのため、経験則のだけの指導になると「合う」選手と「合わない」選手が発生します。「これをやってきたからこの選手は強いんだ」「私はこれをやってきたから」などは、選手の成長を引き出すには運要素が強いです。
どんなに頑張っても、怪我が多かったり、いつまでも足が遅い。
そのため、劣等感が出てしまい落ちこぼれ選手が発生してしまいます。指導者である私たちは、もっとここへの緊張感を持たなければなりません。
そこで、学校やチームの指導は集団指導となるため、個人個人に費やす時間は少ないと思います。私自身もサポートする高校の指導では、とても痛感しています。
これから述べる内容について、念頭に置いておくと、メニューの組み方などに工夫を施すことができるような内容をお伝えしていきます。少しでも役立つ内容になると本望です。

選手の可能性を引き出すことの他にも、同業で活躍される先生やコーチの方々にお役立ちできるように精進していきます👍選手の可能性と陸上業界の発展に向けて一緒に頑張っていきましょう❗️続きへどうぞ⭐️
2.指導の軸で選手の成長は変化する
ここまではトレーニングメニューを組む上で知っておきたいことを簡単に説明させていただきました。
ここからは指導の上で、大切にしていきたいことです。トレーニング内容がどんなに良いものでも、指導者の指導軸が選手にとってどういう物になっているか理解しておかないと、
選手の成長は生まれません。
2-1.「定着型指導」と「生成型指導」について

私が指導する上で大切にしている指導の軸についてお話しいたします。
「定着型指導」とは、「技」の習得が主軸となりがちな指導のことで、「目標ー達成ー評価」になります。
「生成型指導」とは、選手・生徒から自然発生的に学びを生み出す指導のことで、「主題ー探究ー表現」になります。
「定着型指導」は、指導者の到達させたい計画と生徒の到達度にズレが生じてしまう。その計画からズレてしまい、計画についていけなくなってしまった選手・生徒を「落ちこぼれ」となってしまいます。そのため、自ら進んで取り組むための学びの姿勢である「生成型指導」が重要になってくる。
2-2.スポーツを通じて伸ばしていきたいこと

多くの人がスポーツを学生時代に取り組みます。スポーツでは、挨拶や上下関係、時間を守るなど、集団の中でルールやマナーを学ぶ場でもあると思います。しかし、ここまでは一般的には取り組みやすいことでしょう。
社会進出した時に、一番必要になってくることは、自己コントロール力や問題解決力です。スポーツで置き換えると、自分の強みと弱みを理解し、自分の課題に対してどのように打破していくか、探究しそれを表現することが重要であると考えます。この経験はスポーツでは、多く向き合うことが可能である。
そのため、指導者はすぐに答えを教えてしまうのではなく、ヒントや生徒との対話の中で自らの学びの方向に導くことが、私たちの役目だと思います。試合で結果を出せれば、一番いいことですが、それまでのプロセスを一番大切にしていきたいですね。
3.日誌の活用と自由練習

多くの選手を抱える指導者の方は、1人1人に費やせる時間は大なり小なり差があるでしょう。私も高校の指導に入っている中でとても痛感しております。
質問や相談された時はとことん話し込みます。学生選手ですと、部活動以外にも授業や家庭勉強にも取り組まないといけないので、スポーツに打ち込める時間にも限りがあります。
そこで、ヒントやコツが掴めることができれば、後のトレーニングで自ら自分の課題に取り組んでいくでしょう。
しかし、なかなかそれが十分にできないと思います。そこで、大きな役割を果たすのは日誌になります。日誌は自己対話になります。
・その日の目標
・できたこと、できてどう思ったか?
・もしやり直せるなら?
・大きな目標に対して、ヒントになったことや出来事の記録
など、選手それぞれで自分をコーチングします。
日誌を活用した成長のスモールステップについての記事は過去に執筆しておりますので、参考にしてください→ 成長のスモールステップ💡
3-1.日誌の添削について

毎日指導者が多くの選手にお話しすることは難しいでしょう。
そのため、自分のことを見ているかどうか、選手は不安になってしまいます。重要な場面で、意思疎通が取れない可能性もあります。
日々の選手の成長記録である日誌を取り組むことで、選手の不安を取り除けることができ、どんな学びが起きているかも理解してあげることができます。1人1人にコメントを残すことは難しいと思いますが、選手の日誌の中で良いところなどを赤ペンでチェックしてあげるだけでも嬉しいですよね。指導者の負担にならない程度に行いましょう。
そして、それぞれで課題になっていることに対して、取り組むことができる時間を練習時間に組み込んであげます。この時間は、心配ではありますが指導者からの指示はしないほうが望ましいでしょう。選手自ら行動する姿勢を伸ばしていくのです。
この時間は相談することができる時間とわかっておれば、選手自身も不安を取り除ける機会がわかっているので、聞いてあげることもできます。
まとめ
今回は指導する上で大切にしていることを執筆させていただきました。スポーツの指導者である以上子どもたちがスポーツを取り組む経験は、これから大人になっていく上で土台になる部分になる人が多いと思います。
競技で成績を残していくのはもちろんですが、自然発生的に選手から学びを引き出す「生成型指導」を重視した指導は、これからの社会をになっていく子どもたちに必要な要素です。地域のリーダーとなっていく人を多く輩出し、地域が活性化すれば本望です☺️
生成型指導を中心とした陸上クラブを豊橋で設立しようと計画しております。人数的には目にかけれるのは8名〜10名程度ですので、人数限定のクラブにはなりますが、動き出していきたいと思います。
続報をお楽しみに❗️